タロットカードっていつからあるん?
タロットカードって、神秘的で不思議な雰囲気がありますよね。
「いったいいつからこんなカードがあるんやろ?」って思う方も多いと思います。
実は、そのルーツはけっこう昔までさかのぼります。
はじまりは15世紀ごろのヨーロッパ
最初にタロットカードが登場したのは、15世紀のヨーロッパだといわれています。
当時は「マルセイユ版」とよばれるような52枚のカードが描かれていて、主に貴族のあそび道具として使われてたみたいです。
占いとして使われるようになったのはもうちょっと後で、18世紀ごろからだと言われてます。
その頃に「正位置・逆位置」といった読み方の考え方も登場して、占いの道具としての形ができたようです。
現代の定番「ウェイト版タロット」の誕生
そして1909年、イギリスで誕生したのが、今でも世界中でいちばん使われている「ウェイト版タロット」。
これは、神秘学者のE・ウェイトさんと、画家のパメラ・コールマン・スミスさんが協力して作ったものです。
このカードは「ライダー社」という出版社から出たこともあって、「ライダー版」と呼ばれることもあります。
絵柄がカラフルで意味がわかりやすい
ウェイト版は、絵柄がとってもカラフルで、見てるだけでも楽しくなるデザインです。
1枚1枚にしっかり意味が込められていて、タロットの世界観やメッセージが伝わりやすいのが特徴。
初心者さんにとってもとっつきやすいカードなので、「どれにしようかな〜」って迷ってる方には、まずこのウェイト版をおすすめしたいです。
タロットといえば「ウェイト版」が有名だけど、実はほかにもいろんな種類があるんです。
それぞれに特徴があって、使う人の好みによって選ばれています。
✅ウェイト版(ライダー版)
まずは、さっきも出てきた「ウェイト版」。
これがいちばんポピュラーで、初心者さんにも使いやすいって言われてます。
- カラフルな絵柄で、直感的に意味を感じ取りやすい
- 小アルカナ(※数字のカード)にも人物やストーリーが描かれている
- 解説本や情報も多くて、学びやすい
🔰**迷ったらまずはこれ!**という定番中の定番です。
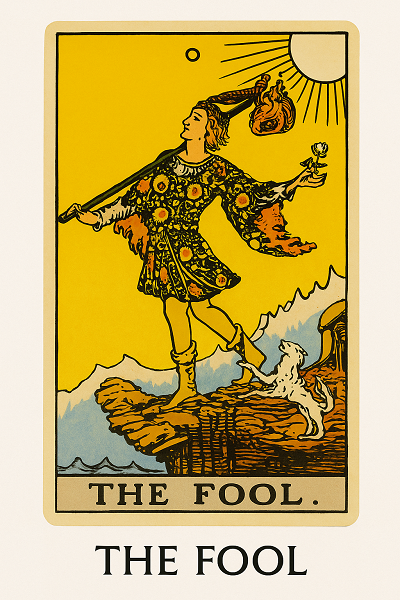
✅マルセイユ版
次に紹介するのが「マルセイユ版」。これは、フランスでよく使われていた伝統的なタロットです。
- 絵柄が素朴で、クラシックな雰囲気
- 小アルカナは数字とスート(剣・カップなど)だけで人物なし
- 絵の情報に頼らず、象徴や数で読み解くタイプ
🔎直感よりも、ルールや象徴でしっかり読みたい人向けとも言えます。

✅トート版
そして、ちょっと上級者向けなのが「トート版」。これは魔術師アレイスター・クロウリーが監修した、ちょっとスピリチュアルでアートなタロットです。
- 抽象的で芸術的なデザイン
- 神秘学やカバラなど、深い知識が詰まってる
- 色彩や象徴の意味もかなり深い
🌌感覚と知識、両方を使って読み解きたい方におすすめです。
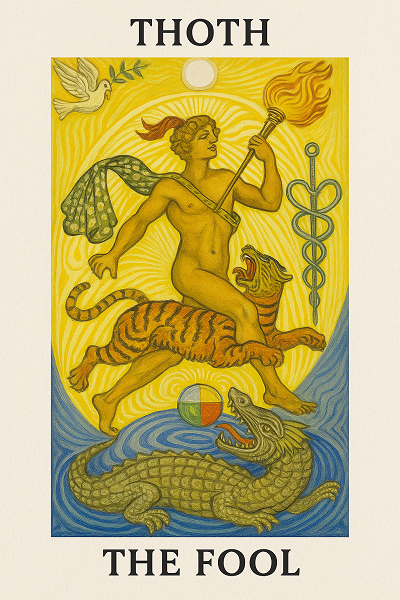
まとめ:自分に合った1枚を見つけよう
それぞれのカードには、そのカードならではの世界観と魅力があります。
「しっくりくる」「見ていてワクワクする」「意味がピンとくる」
そんな“相性”って、けっこう大事なんです。まずは見た目や使い心地で、自分にとって「大切な1枚」を見つけてくださいね✨


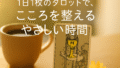
コメント